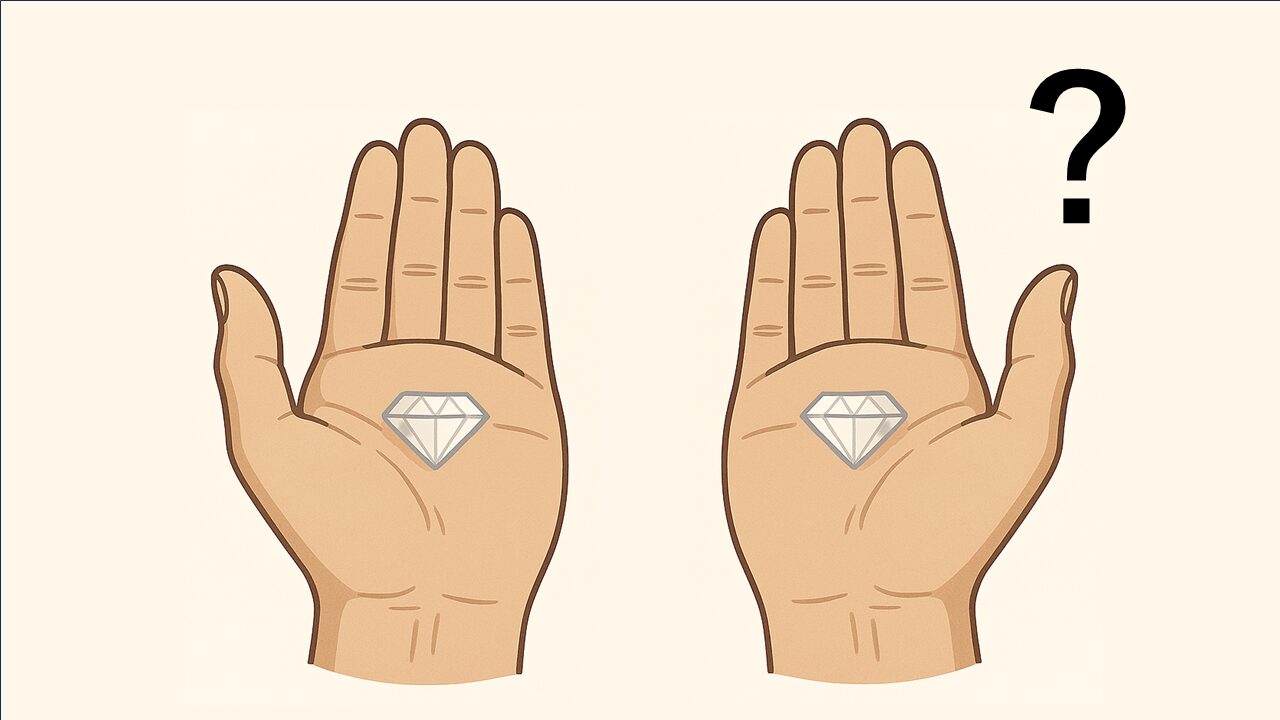人工ダイヤモンドは2000年台になって宝飾品としての利用が広まっており天然物と比べて価格が大幅に安く最近は品質面でも天然ものにキャッチアップしてきています。
手軽にダイヤモンドの美しさを手に入れられる一方、”天然ダイヤモンドの価値が失われてしまわないか” 疑問を抱く方もいるのではないでしょうか。
私の見解としては天然モノはそれとして一定の価値が認められ続けると思います。
※本記事は投資目的でのダイヤモンド購入を推奨するものではありません。話題のひとつとして、気軽にお楽しみください。
天然ダイヤモンドの価値がなくならない3つの理由
同じ輝きなら同等以上の価値が認められる
仮に人工ダイヤモンドと天然ダイヤモンドが全く同じ品質であったとしても、見た目の綺麗さが同じであれば天然ダイヤモンドが人工ダイヤモンドよりも価値が低くなることは考えにくいでしょう。
宝飾品は希少価値が高く評価されやすい
宝飾品は見た目の絶対的な綺麗さはもちろんありますが、”誰よりも美しく”そんな希望を叶えてくれる存在です。希少価値の高い宝飾品は他の人と差をつける必須アイテム。
絶対的な見た目だけではない、希少価値の高い天然物というストーリーは宝飾品の価値を上げてくれます。
着けて楽しむほかに所有欲を満たしてくれるから
見た目の綺麗さに加えて希少性のある宝飾品は持っているだけでも所有欲を満たしてくれます。
”もしかしたら見た目で違いは判りづらいかもしれないけど、このダイヤモンドは他とは違う”、そんな品を持っていれば所有欲の満たされる人が多いのではないでしょうか。
人工ダイヤモンドって何?
ダイヤモンドは炭素原子が固まったもの
ダイヤモンドと黒鉛(炭など)はどちらも炭素原子から成りますが、原子間の結合の違いによって性質が大きく異なります。
ダイヤモンドは炭素原子同士が強い共有結合で三次元的に結びついているため、非常に硬く透明です。
一方、黒鉛では炭素原子が層状に結合し、層同士はファンデルワールス力(静電気引力)でつながっています。
この結合力の違いにより、黒鉛は柔らかく、電気伝導性や潤滑性などの性質を持ちます。
人工ダイヤモンドの作り方
天然ダイヤモンドは、地球の地下深くで高温・高圧の環境下において、長い年月をかけて形成されます。一方、人工ダイヤモンドは「高圧高温法(HPHT)」や「化学気相成長法(CVD)」といった技術によって、短期間で人工的に製造されます。
近年では、天然ダイヤモンドの紛争資金化や児童労働への倫理的な懸念、そしてコスト面での利点から、人工ダイヤモンドの需要と生産が急速に拡大しています。
人工ダイヤモンドの品質は天然もの引けを取らない
人工ダイヤモンドと天然ダイヤモンドを人の目で比べることはかなり難しいようです。それぞれの独特なインクルージョンが残っていれば区別がつくものの、母材としてはほぼ同じため専用の機会を用いた鑑定が必要になってきます。
合成ダイヤモンドの鑑別
HPHT合成ダイヤモンドもCVD合成ダイヤモンドも原石の状態であればすぐに識別することができます。それは結晶原石の形態が天然とは異なるからです。(中略)
しかし、これらが宝飾用にカット・研磨された後では結晶の形態からは天然と識別ができなくなってしまいます。見た目では判らないため、鑑別の技術が重要となります。
合成ダイヤモンド:知っておきたい基礎知識から最新情報まで | 中央宝石研究所(CGL)(参照日時2025/7/12 22:00)
実は昔から使われていた人工ダイヤモンド
ダイヤモンドはかつてより非常に硬い物性からカッターに用いられたり、透過性から光学部品として用いられました。最近の製造技術の発展によって見た目の美しい、比較的大きな人工ダイヤモンドが製造できるようになったことで宝飾品として普及するようになりました。
18世紀後半、ダイヤモンドの成分が炭素であることが発見されて以来、世界中の科学者によって、炭素原子からダイヤモンドを合成する実験が試みられました。そして1955年、総合電機メーカーの「ゼネラル・エレクトリック社(米国/GE)」が、世界で初めて「高温高圧(HPHT)法」によるダイヤモンドの合成に成功。ただ、当初の合成ダイヤモンドはあまりにもサイズが小さく、カット加工が施せる宝飾質レベルの価値がなかったため、主に工業用研磨剤や医療レーザー等の産業用途で使われる程度でした。
(中略)
そんな合成ダイヤモンドが、宝飾用として店頭に広く出まわるようになったのは、つい7~8年前のこと。2010年以降、中国の合成技術が飛躍的に進化し、宝飾質レベルの高品質な製品を低コストで量産できるようになったからです。
合成技術の進化で産業用から宝飾用へ──いま国内外で拡大する合成ダイヤモンド市場 | WORKERS TREND(参照日時2025/7/12 22:00)
人工ダイヤモンドの市場
どこで売っているのか
ダイヤモンドは高額な商品であることから店舗販売が主流です。それは人工ダイヤモンドでも同じ、ただECの広がりはダイヤモンドにも当てはまり、最近ではオンラインで注文が完結するものも出てきています。
鑑定書はあるのか
鑑定書もあります。天然ダイヤモンドより価格が安い人工ダイヤモンドですが、水晶やガラスと間違われたら嫌ですよね。扱った人なら見た目でわかるかもしれませんが。
サステナビリティやエシカルの証として積極的に証明したい場面もあるでしょう。拡大して何とか見える大きさですが、石や台座に”labo grown(=人工)”や専用のマークがついているものもあります。
天然物との違いはあるのか
現状、窒素が混ざったモノが主流の天然ダイヤモンドと、純粋な人工ダイヤモンドでおおよそ機械識別できるそうです。その他に製造過程によって混ざりえる特徴的なインクルージョンで見分けます。
透明ダイヤモンドの母材の物性は全く同じといってもいいくらいで見た目ではわからないとも言われています。
人工・天然ダイヤモンドそれぞれの魅力
人工ダイヤモンドは手軽さが魅力
人工ダイヤモンドは天然ダイヤモンドの10分の1の値段で売られていることもあり、今後の技術革新で益々手軽に手に入れられるようになるでしょう。
天然ダイヤモンドは紛争資金に使われたり、児童労働につながったりと暗い話題が語られることもあります。対して人工ダイヤモンドはそれらの話題とは縁遠いため、サステナビリティー・エシカルの合言葉のもとで見た目だけではない価値が認められています。
天然ダイヤモンドは希少価値の高さが魅力
天然ダイヤモンドは数百万年かけて地球の地下で作られた歴史があり、インクルージョンは個性として世界に二つとない希少性があります。
人工物で物的な欲求が満たされた後、次に向かうのは特別感(=希少性)ではないでしょうか。
コーヒーや回転ずしの例から学んでみよう
この記事のタイトルは「天然ダイヤモンドが売れなくなるのか」でした。タイトル回収も兼ねてコーヒーや回転ずしを例に考えてみます。
コンビニコーヒーによって喫茶店が潰れたか
コンビニコーヒーの市場拡大はすさまじいですね。手軽な値段でそれなりに美味しいコーヒーが飲めるので納得。私も利用する機会があります。
それによって喫茶店がつぶれるなんて声もありましたが、意外とそうでもありませんね。
・1981年 154,630店舗 (喫茶店店舗数のピーク)
・2012年 70,454店舗
・2013年 セブンカフェ導入
・2021年 58,669店舗
※店舗数は全日本コーヒー協会より
多少減っていますがカフェブームからの縮小の流れでしょう。コンビニコーヒーの相手は手軽にテイクアウトできる飲み物、ペットボトルや缶入りの清涼飲料水ですね。むしろテイクアウトコーヒーの新たな市場を作ったことで喫茶店にも好影響があったという声もあります。
回転ずしにも同じことが言えそうですね。回転ずしチェーンに行くのは家族連れが多く、競合相手はファミレスなど。高級寿司屋や港町の寿司店の客層は高所得者や観光客が多いのですみわけができますね。
人工ダイヤモンドのターゲットは手軽に美しさを求める人々
人工ダイヤモンドを求める人は手軽にその美しさを手に入れたい、実用的な考えの人が多いのではないでしょうか。そうなれば競合は天然ダイヤモンドではなく他の(クォーツやエメラルドなどの)人工宝石と考えるのが自然でしょう。
サステナブルやエシカルも重要ですがそれらの課題は業界が乗り越えてくると思っています。これまでにもコーヒー豆、カカオ、スズ、ロブスター、綿花など生産方法が問題視された品物は数多くあります。未解決の課題もありますが認証制度によってサステナブルやエシカルを謳っている商品はたくさんあります。天然ダイヤモンドにも認証制度が設けられ、これらの問題はクリアされる気がします。
※本記事は投資目的でのダイヤモンド購入を推奨するものではありません。話題のひとつとして、気軽にお楽しみください。
いかがでしょうか。最近人工ダイヤモンドの特集を見たので気になって自分でも今後を占ってみました。今後の動向はその時になってみなければわかりませんが、綺麗を楽しめる新しい選択肢が増えたことは純粋に良いことと思いますね。